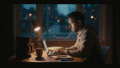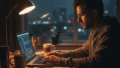結果どうなったか。最初の1日は、正直ほとんど進まなかった。それでも、長年しまい込んでいた“自分で稼ぐ感覚”が、固まった氷のひび割れみたいにパキッと音を立てた。2回、3回と積み重ねるうちに、収入という数字よりも先に、自己効力感という見えない資産が増えていくのを実感します。やがて、それは本業の提案力や意思決定の速さにも波及した。副業は本業の敵じゃない。設計次第で、むしろ最高の共同運用者になる――そう気づいた瞬間、人生のチャートに上昇トレンドが描かれ始めました。
この記事では、僕自身の試行錯誤と、人事・社労士に直接確認した一次情報を土台に、「有給中に副業は本当にOKか?」「どこまでが合法ラインで、どこからが落とし穴か?」を余すことなく解説します。感情に寄り添いながら、数字とルールで支える。節約は我慢じゃない。副業は苦労じゃない。投資はギャンブルじゃない。――お金の流れをデザインすれば、人生の景色は変わる。その設計図の最初の1ページを、ここから一緒に開きましょう。
- 有給休暇中に副業はできる?──“法律のグレーゾーン”に光を当てる
- 有給中に副業したら労働時間はどうなる?──知られざる“通算ルール”の真実
- 人事担当者に聞いた“バレる・バレない”の現実──沈黙より「信頼」で守る副業戦略
- 社労士が語る「合法ライン」と「落とし穴」──ルールの“地図”を持たないまま歩く危うさ
- 有給を“副業デー”にするための安全なステップ3──リスクを避けて「自由時間」を資産に変える方法
- 有給副業で得られた“お金以外”のリターン──数字には表れない「人生の含み益」
- FAQ:有給×副業のよくある質問──“グレーな疑問”をクリアにしてから動こう
- まとめ:有給は“未来を作る時間”にできる──休みを「投資」に変えるという発想
有給休暇中に副業はできる?──“法律のグレーゾーン”に光を当てる

まず最初にハッキリ伝えておきたい。
有給休暇中に副業をしても、法律的には違法ではありません。
労働基準法第39条は、有給休暇の「使い道」について制限を設けていません。つまり、有給とは
「自由に使える時間を取り戻すための権利」。その時間を旅行に使おうが、資格の勉強に使おうが、あるいは副業に使おうが、法の枠組みから見ればすべて“OK”なのです。
僕がこの事実を知ったとき、正直ホッとしました。「休む」という言葉は“何もしないこと”のように聞こえるけれど、実は
“自分のために時間を再配分すること”でもある。たとえるなら、有給は
“時間の定期預金”。使わなければ金利もつかないし、引き出してこそ価値がある。
厚生労働省『副業・兼業の促進に関するガイドライン』(令和4年改定)にも、こう明記されています。
「労働者の多様なキャリア形成を支援するため、副業・兼業を促進する」
つまり国としても、「副業を前向きに活用しよう」という流れを明確に打ち出しているわけです。では、なぜ「有給で副業してはいけない」と思い込んでしまう人が多いのか?その原因は、
“会社の就業規則”にあります。
実は、ガイドラインは「努力義務」にすぎず、企業が従わなければならない“法律”ではありません。だから、会社によっては依然として「副業禁止」「事前許可制」などのルールを設けているところもある。この点を見落とすと、法的にはセーフでも
“社内ルール的にはアウト”という落とし穴にハマる可能性がある。
僕の勤めていた会社も例にもれず「原則副業禁止」でした。けれどある日、思い切って人事担当者に相談してみたんです。すると返ってきたのは意外な答え――
「競合じゃなければ、会社に利益相反しない範囲でなら許可できるケースもあるよ」。
その瞬間、僕は思いました。
――“敵”だと思っていた壁は、案外「相談」というドアをつければ通れるのかもしれない、と。
副業を黙って始めるのは、夜中に公園のフェンスをよじ登るようなもの。やってやれないことはないけれど、いつか足を滑らせるリスクがある。だったら、正面からゲートを通ればいい。鍵は
「誠実な相談」と「ルールの理解」。それが、有給を“安心して副業デーに変える”ための第一歩なんです。
有給中に副業したら労働時間はどうなる?──知られざる“通算ルール”の真実

副業にまつわる誤解の中で、特にややこしく、そして“見落とされがち”なのがこの「労働時間の通算」というルールです。
ざっくり言うと、これは「2つの会社で働いた時間を足し算して、1日の労働時間として扱う」という決まり。
たとえば、本業で8時間働き、副業でさらに3時間働けば、合計11時間。法律上は、8時間を超えた3時間分が“残業”としてカウントされる可能性がある、というわけです。
この制度を初めて知ったとき、僕は思わず「え、そんなルールまであるの?」とつぶやきました。
でも、よく考えれば当たり前の話。法律の目的は「働きすぎを防ぐこと」。
つまり、どんな働き方をしていても、体を壊してしまっては意味がない――それが“通算ルール”の根底にある考え方なんです。
ただし、ここで重要なのが「どんな副業が通算の対象になるのか」という点。
実はこのルールが適用されるのは、両方が「雇用契約」でつながっている場合だけなんです。
たとえば、昼は会社員、夜はコンビニでアルバイト――このように2つの雇用関係がある場合は、労働時間が通算される可能性があります。
一方で、僕のように「業務委託」や「請負契約」で副業をしている場合、つまり「時間で管理されていない働き方」をしているなら、このルールは適用されません。
言い換えれば、会社に雇われて働く“時間労働”ではなく、自分のスキルを軸に“成果で報酬を得る”働き方なら、通算の枠から外れるということです。
有給休暇中にライティングやデザイン、動画編集などをしても、それは“働いている”というより“創っている”。
時間の束縛ではなく、成果を生み出す自由な労働――その違いが大きいんです。
参考:neutral-sr.com『副業で労働時間を通算するケースとしないケース』では、
「労働契約による副業は通算対象、業務委託は対象外」と明確にされています。
僕はこの点について実際に社労士に確認しました。
その回答はシンプルで、しかし本質的でした。
「時間で管理されていない働き方をしている限り、労働時間通算のリスクはほとんどない。
ただし、“責任の範囲”はあなた自身が引き受けることになる。」
つまり、自由の代わりに、自己管理という義務が生まれるということです。
僕はこの言葉に、どこか投資の世界の教訓を感じました。
“リスクを理解すれば、それはリスクではなくなる”――まさにそれです。
有給を使って副業をするという選択は、ただの時間の使い方ではなく、「働き方のリバランス」だと僕は思っています。
法律を知らずに突っ込むのはノーガードで投資するようなもの。
でも、ルールを理解して設計すれば、有給という1日は“損しない副業時間”に変えられる。
通算ルールを知ることは、そのための第一歩なんです。
人事担当者に聞いた“バレる・バレない”の現実──沈黙より「信頼」で守る副業戦略

副業の話をすると、ほぼ100%返ってくる質問があります。
それは、「会社にバレませんか?」という一言。
正直、その気持ちは痛いほどわかります。
僕も最初は“スパイ映画の主人公”みたいに、バレないように神経を尖らせていました。
家で仕事をするときはカーテンを閉め、プロフィールには会社名を出さず、報酬の入金口座も分ける。
でも、そんな息を潜めた副業生活は、長くは続きませんでした。
どこかで心が疲れてしまうからです。
では、実際のところ「バレる」原因は何なのか?
僕は思い切って、人事担当者にストレートに聞いてみました。
返ってきた答えは、驚くほど現実的なものでした。
- 住民税の特別徴収で、副業収入が見えてしまうケース
- SNSやクラウドワークスなど、ネット上の活動から発覚するケース
- 同僚や取引先の口コミから、間接的に伝わってしまうケース
特に注意すべきは「住民税」です。
会社員の場合、給与所得に対する住民税は通常“特別徴収”といって、会社がまとめて納税する仕組み。
そこに副業収入が合算されると、「あれ?この人、去年より税金高くない?」と人事部が気づくわけです。
僕はこれを防ぐために、確定申告を自分で行い、住民税を『普通徴収』に設定しました。
これで、副業分の住民税は自分で納付する形になり、会社経由で知られる心配はありません。
とはいえ、これは“あくまで制度上のテクニック”。
バレないことを目的に動くと、どうしても精神的な負担が増えてしまいます。
人事担当者が言っていた言葉が、今でも心に残っています。
「バレないようにするより、ルールに沿って“正直に申告する”方が、結果的に信頼される。」
最初はその言葉を聞いて、正直「理想論だな」と思いました。
でも、勇気を出して副業を正式に申請してみたら、予想外の反応が返ってきたんです。
上司は「へぇ、どんな仕事してるの?」と興味津々で、同僚からも「自分もやってみたい」と声をかけられた。
つまり、“隠す存在”から“刺激を与える存在”に変わったんです。
副業は、バレるか・バレないかのゲームじゃありません。
信頼をベースに設計すれば、会社の中で孤立するどころか、むしろ新しい価値を生む。
それを僕は、自分の体験で確信しました。
副業を“隠す秘密”ではなく、“共有できる挑戦”に変えた瞬間――
僕の働き方の自由度は、数字以上に大きく跳ね上がったのです。
社労士が語る「合法ライン」と「落とし穴」──ルールの“地図”を持たないまま歩く危うさ

副業をしている人の多くが気にするのは、「どこまでがセーフで、どこからがアウトなのか?」という境界線です。
僕も最初は、“このくらいなら大丈夫だろう”という感覚で動いていました。
でも、社労士の先生に会って話を聞いたとき、その曖昧な線がいかに危ういものかを痛感しました。
先生の言葉を借りるなら、副業の世界は「自由な道のようで、法の白線がちゃんと引かれている道路」だということ。
その白線を見落としたまま走ると、気づかないうちに“違反”のレーンに入ってしまう可能性があるんです。
社労士の先生に整理してもらった内容を、わかりやすくまとめるとこうなります。
✅ 合法ライン(安心して走れるレーン)
- 会社の就業規則で明確に禁止されていないこと。
- 労働時間通算の必要がない働き方をしていること(業務委託・成果報酬型など)。
- 本業と競合関係にない仕事であること(情報漏えいのリスクがない)。
この3つを押さえておけば、法的にも倫理的にも“大きく外れる”ことはありません。
特に3つ目の「競合関係がないか」は、いわば副業における“ゴールデンルール”。
本業で得た情報を副業で使うのは、会社の信頼を裏切ることにもなりかねません。
⚠️ 落とし穴(見えにくい段差)
- 本業と似た仕事をして“競業行為”と見なされる。
- 副業の疲労で本業のパフォーマンスが下がる。
- 副業中の事故や病気が労災の対象外になる。
社労士の先生は、こう言いました。
「副業で一番危険なのは、“バレないと思い込むこと”。
ルールを知らないまま動くのは、地図を持たずに山へ入るようなものです。」
中でも注意したいのは、やはり“競業禁止”。
同業他社で働く、副業の中で本業の顧客情報を扱う――こうした行為は、
たとえ“悪意がなくても”懲戒の対象になるケースがあります。
僕も以前、ライティング案件を受ける際に「テーマが自社メディアと近い」と感じて断ったことがあります。
そのとき社労士の先生に言われた言葉が忘れられません。
「たとえ1円の仕事でも、信用を失えば損失はゼロでは済まない。
お金の世界は、信頼という“無形資産”で回っているんです。」
副業のリスクは、派手なトラブルではなく、静かに起こる“信頼の崩落”から始まる。
だからこそ、ルールを知り、白線の内側で自分のスピードを保つことが大切です。
「合法ライン」は安全運転のための地図であり、
「落とし穴」はブレーキの効かない坂道のようなもの。
どちらも理解して初めて、副業は「自由」と「安心」を両立できる道になるのだと思います。
参考:esmailsr.com『副業・兼業労働者の労務管理』によると、
「本業と副業が同業であれば、競業行為と見なされる可能性が高い」と明記されています。
有給を“副業デー”にするための安全なステップ3──リスクを避けて「自由時間」を資産に変える方法

有給休暇を「ただの休み」にするか、「未来を育てる時間」にするか。
その差は、たった3つのステップで決まります。
これは、僕自身が何度も試行錯誤しながらたどり着いた“安全に攻める”副業デザインの手順です。
① 会社の規程を必ず確認する──ルールを知ることは最大の防御
副業を始める前に、最初にやるべきことは「就業規則を読む」ことです。
多くの人はここを飛ばして「多分大丈夫だろう」と始めてしまいますが、それは地図を見ずに登山するようなもの。
副業禁止、許可制、届出制──会社によってルールはまったく違います。
僕の会社の場合、「競業でなければ申請次第で許可可」と書かれていました。
つまり、きちんと筋を通せば、ドアは開く。
不明点は人事に確認し、メールなどで記録を残しておくのがベストです。
その一通のメールが、後々あなたを守る“安全証書”になります。
社労士の先生もこう言っていました。
「就業規則を読むことは、敵の弱点を探すことではなく、自分の防具を整えることです」
まさにその通りだと思います。
② 副業を「業務委託型」にする──時間に縛られない働き方を選ぶ
次に大切なのは、副業の“形を整える”こと。
クラウドソーシングやスキルシェアなど、「業務委託」や「請負契約」といった時間に縛られないスタイルを選ぶのが理想です。
理由はシンプル。「労働時間の通算」のリスクを避けるためです。
雇用契約で働くと、法律上、本業と副業の時間を足して計算する必要がありますが、業務委託ならその対象外。
つまり、働く時間を“自分でデザインできる”わけです。
僕自身も、ライティングやデザインの仕事を請けるときは、
「この日だけは副業デー」と決めて有給を使い、“集中して創る時間”にしています。
この形式だと、本業に支障を出さずに収入を積み上げられるうえ、時間の使い方にも責任感が芽生える。
副業を通して、むしろ本業の生産性が上がったのは自分でも驚きでした。
副業とは“もう一つの仕事”ではなく、“もう一つの成長装置”です。
自分で仕事を作る側に立つと、同じ8時間でも「使い方の濃度」がまるで変わる。
それこそが業務委託型の醍醐味です。
③ 有給を“目的のある休暇”に変える──時間を「投資資産」に転換する
最後のステップは、“有給を意図的に使う”という発想です。
ただ休むのではなく、計画的に「副業デー」としてブロックしておく。
たとえば月に1度、金曜日を休みにして、自分のスキルを育てる日にする。
それだけで、1年後には12日分の“未来を動かす日”が積み上がります。
僕はこれを、「時間のドルコスト平均法」と呼んでいます。
お金と同じで、コツコツと一定のペースで時間を投資することで、スキルや収入という成果が安定して積み上がる。
逆に、思いつきで動くとリターンも波打ちます。
1日の有給を「新しい収入を作る日」に変える。
それはつまり、時間をお金に換える練習です。
最初は小さな成果でも、その感覚が身につくと、“働かされる側”から“働きをデザインする側”へと意識が変わります。
副業の成功は、特別な才能よりも「仕組みとリズム」で決まります。
そして、有給という仕組みは、実はそれを練習するのに最適な舞台なんです。
会社のルールを理解し、時間の構造を整え、意図を持って休む。
この3つのステップを踏むだけで、有給は単なる「休暇」ではなく、「未来を設計する投資口座」に変わります。
有給副業で得られた“お金以外”のリターン──数字には表れない「人生の含み益」

僕が有給を使って副業を始めてから、確かに収入は増えました。
銀行口座の数字が少しずつ膨らんでいくのを見て、「ああ、ちゃんと形になっている」と嬉しくなったのを覚えています。
でも、正直に言うと――その“増えたお金”よりも大きかったのは、「自分にもまだ伸びしろがある」と感じたことでした。
長く同じ会社にいると、成長の天井が見える瞬間があります。
どれだけ努力しても評価の基準は変わらないし、挑戦より安定が優先される。
そんな日々の中で、有給を“副業デー”に変えるという小さな行動は、
まるで固まった水面に一滴のインクを落とすようなものでした。
最初は小さな揺らぎだったのに、気づけばその波紋が、自分の考え方全体を変えていたんです。
副業を通じて出会った人たちは、肩書きも年齢もバラバラでした。
デザイナー、動画編集者、ブロガー、フリーランスのエンジニア。
彼らに共通していたのは、「自分の時間を自分で設計している」という姿勢。
僕はその空気に触れるたび、会社という小さな箱の外にも、
“仕事を楽しむ自由”があることを実感しました。
そして、副業を通じて新しいスキルを学ぶことは、
単に収入を増やすためではなく、“自分の市場価値を再評価するプロセス”でもありました。
例えば、ライティングやマーケティングの知識を学ぶうちに、
本業でのプレゼン資料や提案書の質まで上がっていった。
副業で磨いたスキルが、本業を後押しする――そんな“相乗効果”は想像以上でした。
つまり、有給副業で得られたのは、数字では測れない「自信」と「再発見」です。
お金は増えるもの、でも自信は育てるもの。
副業は、その“自己成長の温室”になりました。
有給休暇は、たしかに「休むための権利」です。
けれど、僕にとってはそれが「未来を育てる時間」に変わりました。
仕事に疲れたときに使う“逃げ道”ではなく、
未来に向かって自分を再構築するための“滑走路”だったんです。
お金という数字は増えたり減ったりします。
でも、経験と自信という“人生の含み益”は、失われません。
だから僕はこれからも、有給を“休暇”ではなく“投資”として使っていこうと思います。
FAQ:有給×副業のよくある質問──“グレーな疑問”をクリアにしてから動こう
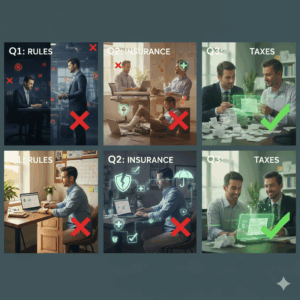
副業に踏み出そうとすると、誰もが一度はつまずくのが「法律」と「会社ルール」という2つの壁です。
SNSでは「バレなければ大丈夫」「みんなやってる」と軽く言われがちですが、実際の現場はそんなに単純じゃありません。
僕自身、最初の一歩を踏み出す前に何度も社労士や税理士に確認を重ねました。
ここでは、そのときによく出た質問を、実体験と専門家の回答をもとに整理しておきます。
Q1. 有給中に副業したら懲戒対象になりますか?
この質問、実は多くの人が勘違いしています。
「有給中に働く=違法」ではありません。
問題になるのは、就業規則で副業が禁止されている場合や、競業行為にあたる場合です。
つまり、同業他社で働いたり、本業で得た情報を副業に使ったりすれば、懲戒のリスクがあります。
でも、会社の利益と競合しない、個人スキルを活かした業務委託や在宅ワークであれば問題ありません。
僕が相談した社労士の先生の言葉を借りるなら、
「副業で問われるのは“何をしたか”よりも“どんな関係で働いたか”」ということ。
つまり、契約形態と業務内容の線引きを明確にしておけば、安全に動けるということです。
Q2. 有給中の副業で事故にあったら?
副業中の事故は、基本的に副業先の労災保険が適用されます。
ただし、雇用契約ではなく業務委託として働いている場合は、労災の対象外になるケースもあります。
この場合、自分で労災保険特別加入制度に申し込むことでリスクを減らすことができます。
実際、フリーランスや副業ワーカーの中には、こうした保険を活用している人が増えています。
僕は社労士に「保険は“安心の会費”だと思って払っておくといい」と言われました。
確かに、もしもの時に守ってくれる“安全ネット”があると、心のブレーキが少し緩む。
そうすると、挑戦のアクセルを踏みやすくなるんです。
Q3. 副業収入がある場合、確定申告は必要?
これは意外と知られていませんが、年間20万円を超える副業収入がある場合は確定申告が必要です。
逆に、20万円以下でも住民税の申告は必要なケースがあります。
副業収入が少ないうちは軽く見がちですが、税金の管理を怠ると、思わぬ形で会社にバレるリスクがあります。
僕は副業を始めた年、確定申告の書類作成に半日かかりました。
でも、それ以降はクラウド会計ソフトを使って自動化。
今では数字を見るのが苦にならず、むしろ「自分の経営をしている感覚」が生まれています。
税理士の先生が教えてくれた言葉を最後に。
「副業とは、収入を増やす練習ではなく、“お金と責任をコントロールする練習”なんですよ」
これは僕が今でも大事にしている考え方です。
つまり、有給中の副業を安全に続けるコツは、ルール・保険・税金という“3つの基礎”を理解しておくこと。
それが、安心して走り出すためのエンジンオイルです。
知識はあなたを守り、行動はあなたを変える。
この2つが合わさったとき、有給副業は「危険な挑戦」ではなく、「人生を再設計する手段」になります。
まとめ:有給は“未来を作る時間”にできる──休みを「投資」に変えるという発想

ここまで読んでくれたあなたに、僕が一番伝えたいのはこの一文です。
「有給休暇は、休むためだけの時間ではなく、“未来を作るための資産”にできる」ということ。
副業というと、どうしても“お金を稼ぐ手段”というイメージが先に立ちます。
けれど、僕が有給を使って副業を始めて気づいたのは、収入よりも「自分の可能性」を取り戻すことこそ最大のリターンだという事実でした。
法律的に見ても、有給中に副業を行うことは問題ありません。
ただし、ルールを理解し、正しい枠組みの中で行うことが大前提です。
ここで再確認しておきたいのが、次の3つの原則。
- 就業規則を確認する。
自社が副業を禁止していないか、許可や届出が必要かを必ずチェックする。 - 労働時間の通算対象にならない働き方を選ぶ。
雇用契約ではなく、成果報酬・業務委託など時間拘束のない形を意識する。 - 本業に支障を出さない。
副業は「本業を支えるもう一つの柱」であることを忘れずに。
この3つを守れば、有給という時間は「ただ消える日数」から「未来を設計する投資資源」へと変わります。
僕はこの感覚を、株式投資の“長期保有”に似ていると感じています。
目先の利益ではなく、時間をかけて成長を育てる――それが副業の本質です。
一歩を踏み出す前は、誰だって怖い。
けれど、知識というコンパスを持って進めば、恐れは慎重さに変わり、慎重さは継続力になります。
その継続が、やがて自分の人生の“複利”となって返ってくるんです。
僕の結論は、シンプルで、でも揺るぎない。
「ルールを理解して動けば、有給は“未来を変える時間”になる。」
あなたの“次の有給”が、休息ではなく成長の一歩になることを、心から願っています。